No.0053 天地始まりの時
その2「葦牙(あしかび)って何?」

ところで、古代の出雲大社の復元図って見たことはありますか?当時日本で最も高い建築物であったという記録や幾度となく倒れた記録、さらには銅鐸(どうたく)や土器の図柄から復元模型も作られています。
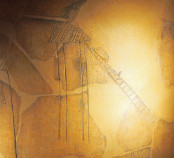

この建物、ちょっと不思議に思いませんか?ただ高さが必要ならば山中に作るのが賢明です。山中に平たい場所を造成して社(やしろ)を作り、階段は山の斜面を利用すれば良い。でも古代の人は平地に高層建築を作っています。なぜでしょう?
理由は
水面から突き出る葦牙(あしかび)のように高く垂直な柱を建てて、その先に天(あめ)の社(やしろ)を再現したかったのです。
山中に現存する神社もあるよという声も聞こえそうです。これは簡単な理由です。山に由来する神様の社(やしろ)は山に作られます。
葦牙(あしかび)というのは葦(あし、よし)という植物の発芽したものを言います。葦はイネ科の植物なので水辺に水面から突き出るよう芽を出します。

ところで、古代の出雲大社の復元図って見たことはありますか?当時日本で最も高い建築物であったという記録や幾度となく倒れた記録、さらには銅鐸(どうたく)や土器の図柄から復元模型も作られています。
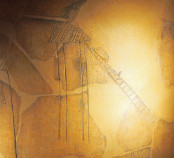

この建物、ちょっと不思議に思いませんか?ただ高さが必要ならば山中に作るのが賢明です。山中に平たい場所を造成して社(やしろ)を作り、階段は山の斜面を利用すれば良い。でも古代の人は平地に高層建築を作っています。なぜでしょう?
理由は
「葦牙(あしかび)のように燃え上がった先に天がある」
ということなのです。水面から突き出る葦牙(あしかび)のように高く垂直な柱を建てて、その先に天(あめ)の社(やしろ)を再現したかったのです。
山中に現存する神社もあるよという声も聞こえそうです。これは簡単な理由です。山に由来する神様の社(やしろ)は山に作られます。